*このメールマガジンは、私・神田と直接名刺交換させて頂いた方々に送信させて頂いております。(今後、送信不要の方につきましては、最後にある送信停止の手続きを行って頂くよう、宜しくお願いいたします。)
「やってみなはれの極意⑥」~日本経済復興のキーワードは「不易流行」にあり~ みなさん、こんにちは。(株)チームフォース代表の神田です。今年に入ってから日本企業の株価が上昇傾向にあります。これは海外投資家が日本企業の実力(稼ぐ力)を再評価し、日本株に大きく投資しはじめたことによるものです。昨年の4月に来日した有名な投資家であるウォーレン・バフェット氏は日本の株に対して高い評価を示し、「今後値上がりが期待される日本株市場の特定の銘柄に興味を持っている」と語っています。彼の投資企業の条件は「株価が割安であること」と「事業内容が理解できること」。株価が割安であることを示す指標の一つにPBR(株価純資産倍率)がありますが、日本では上場企業の半数以上が1倍未満で、企業価値に比して市場からの評価が低すぎることが日本株への投資を促進する大きな要因であるとも語っています。(*株価純資産倍率…株価純資産倍率は、企業の株価をその企業の純資産で割った値を示す指標)
みなさん、こんにちは。(株)チームフォース代表の神田です。今年に入ってから日本企業の株価が上昇傾向にあります。これは海外投資家が日本企業の実力(稼ぐ力)を再評価し、日本株に大きく投資しはじめたことによるものです。昨年の4月に来日した有名な投資家であるウォーレン・バフェット氏は日本の株に対して高い評価を示し、「今後値上がりが期待される日本株市場の特定の銘柄に興味を持っている」と語っています。彼の投資企業の条件は「株価が割安であること」と「事業内容が理解できること」。株価が割安であることを示す指標の一つにPBR(株価純資産倍率)がありますが、日本では上場企業の半数以上が1倍未満で、企業価値に比して市場からの評価が低すぎることが日本株への投資を促進する大きな要因であるとも語っています。(*株価純資産倍率…株価純資産倍率は、企業の株価をその企業の純資産で割った値を示す指標)
ここ直近までの日本は「失われた30年」という言葉に代表されるように、世界の経済成長から一人取り残され、アメリカに次ぐ第二の経済大国と言われたかつてのイメージはすっかり失われてしまいました。なぜ日本がこの30年間、活力を失い続けてしまったのでしょうか?直接のきっかけは1991年に発生したバブル景気の崩壊で、株価や不動産価格の急落により、多くの企業や個人が資産を失い、信用不安や経済の停滞が広がったことにあります。それまで続いていた高度経済成長が終焉にさしかかり、成長の鈍化や労働人口の減少、そして少子高齢化などの構造的な課題が経済の持続的な成長を阻害しました。
加えて労働市場の柔軟性の欠如、高い規制、そして保守的な企業文化などが、イノベーションや成長を妨げたのです。その間の日本の大企業の凋落にも目を覆うものがありました。日本経済が低空飛行を続けたこの間、日本企業は大きく地盤沈下しました。企業の時価総額を見ても、平成元年には世界のトップ5を日本企業が独占し、上位30社の約7割を日本企業が占めていましたが、平成31年(平成最後の年)には上位30社に残った日本企業は1社もなくなりました(最高位はトヨタ自動車の43位)。つまり日本経済の低迷はかつて世界を席捲した日本を代表する大企業の凋落と共に進んできたということになります。 このように日本経済の長期にわたる低迷の原因については前述した通りですが、そのきっかけはバブル崩壊であったのは間違いないとしても、長期低迷の最大の要因は「デジタル革命に乗り遅れた」ことにあると私は考えています。日本の失われた30年と世界のデジタル革命の勃興はその期間がぴったり重なっていて、このデジタル革命の起点は1995年ごろのインターネットの爆発的普及からであり、それを基盤に2000年代になってからスマートフォンやクラウドが誕生し、米国のGAFAが躍進し、ChatGPTなどの生成AI(人工知能)が登場して現在に至っています。
このように日本経済の長期にわたる低迷の原因については前述した通りですが、そのきっかけはバブル崩壊であったのは間違いないとしても、長期低迷の最大の要因は「デジタル革命に乗り遅れた」ことにあると私は考えています。日本の失われた30年と世界のデジタル革命の勃興はその期間がぴったり重なっていて、このデジタル革命の起点は1995年ごろのインターネットの爆発的普及からであり、それを基盤に2000年代になってからスマートフォンやクラウドが誕生し、米国のGAFAが躍進し、ChatGPTなどの生成AI(人工知能)が登場して現在に至っています。
これは日本の主なテック企業(ITなどのテクノロジーを駆使したビジネスを展開している企業)に言えることですが、新たな独自のビジネスモデルの創出によって、市場や顧客を日本国内だけではなくグローバルに展開・獲得できたかどうかが、企業が大きく発展できるかどうかの分かれ目になったと考えます。つまり日本の企業が、かつてのソニーの「ウオークマン」などのような世界が必要とする画期的な製品やサービスを生みだせなかったことがその要因といえるでしょう。
ではなぜその30年間の間に、グローバル展開できるような財やサービスが生まれなかったのでしょうか?この「問い」を深く掘下げていくことが、今後の日本企業の復活のヒントを探る鍵になります。それは大きく変化する経営環境の中で将来の新たなビジネスモデルの創出に向けての「イノベーション」への積極的な投資を怠ったことにあると私は考えています。さらに根本的な要因を突き詰めていくと、日本企業の経営者の考え方や意思決定そのものに帰結するのです。世界第二の経済大国とあがめられ、「ジャパンアズナンバーワン」という著書が売れたことをよそ眼に、日本企業は2000年代に入って起こったデジタル革命の流れを軽視し、新たな付加価値の高いグローバルなビジネスモデルの探求を怠ってしまったのです。 昭和・平成の大企業の生え抜きのサラリーマン社長は、一般的な任期といわれる5年前後の期間、大きな失敗をせずに無難に経営の舵取り行うことに専心し、短期的な視点に基づいた経営を重視してきました。シリコンバレーのスタートアップの新興企業が、死に物狂いで資金を集め、大きなリスクを背負って大胆な発想でイノベーティブな経営を推進してきたのとはまったく対照的です。つまりかつての日本は経営のトップが自ら挑戦することを避け、安全な道を選択し続けたことで、のちに「企業成長の鈍化」という大きなツケが回ってきたと私は考えています。そしてそのような経営者の考え方は「ヒト」への投資への意識の薄さにつながりました。
昭和・平成の大企業の生え抜きのサラリーマン社長は、一般的な任期といわれる5年前後の期間、大きな失敗をせずに無難に経営の舵取り行うことに専心し、短期的な視点に基づいた経営を重視してきました。シリコンバレーのスタートアップの新興企業が、死に物狂いで資金を集め、大きなリスクを背負って大胆な発想でイノベーティブな経営を推進してきたのとはまったく対照的です。つまりかつての日本は経営のトップが自ら挑戦することを避け、安全な道を選択し続けたことで、のちに「企業成長の鈍化」という大きなツケが回ってきたと私は考えています。そしてそのような経営者の考え方は「ヒト」への投資への意識の薄さにつながりました。
昨今改めて人的資本経営の重要性が叫ばれていますが、やはり企業がイノベーションを生み出す根源は「ヒト」にあります。組織に対するエンゲージメントが高く、自由闊達で心理的安全性の高い組織にしか価値のあるイノベーションは生まれません。一方で、このような日本の環境で働く社員の仕事への熱意や取組姿勢も低迷していきました。米ギャラップ社のエンゲージメント調査(2017年)によると、日本企業の「熱意あふれる社員」の割合は6%にとどまっていて、これは米国企業の32%と比べて際立って低く、調査した139カ国中132位と最下位クラスに低迷しています。こうしたデータを重ね合わせると、企業の中で組織の上(経営層)から下(若手層)までの構成員が縮こまりながら、できること・与えられたことだけを淡々とこなしてきた様子が伺えます。
しかしながらこのような日本にも直近でようやく復調の兆しが見え始めてきました。前述した通り株価の上昇、それに伴う企業業績の向上、グローバル企業の積極的な海外展開など、今まで消極的だった経営姿勢が積極性を見せ、かつて名を馳せたの日本企業が息を吹き返しつつあります。そのような兆候を表している代表的な企業が日本製鉄です。高度成長時代の重厚長大産業において旧来型の日本的経営のイメージの強いこの企業の復活の軌跡を「日本製鉄の転生(上阪欣史著・日経PB社)」から少し紹介させて頂くと、 日本製鉄の「転生」のものがたりは、2019年に橋本英二氏が社長に就任する頃からはじまる。主力の国内製鉄事業が赤字に落ち込み、回復の見通しも立たない状況の中、まずは構造改革を進めるために製鉄所の象徴である「高炉」の廃止をあっという間に次々と決定し、長年供給先に握られていた価格主導権を、値上げに踏み切ることで取り戻し、提供する製品の付加価値を高めることに成功した。その傍ら海外事業を拡大すべく矢継ぎ早の巨額投資に打って出た。10万人以上の従業員を抱える大きさこそ変わらないが、その重厚長大な企業体質の足取りは明らかに軽くスピイーディーになった。
日本製鉄の「転生」のものがたりは、2019年に橋本英二氏が社長に就任する頃からはじまる。主力の国内製鉄事業が赤字に落ち込み、回復の見通しも立たない状況の中、まずは構造改革を進めるために製鉄所の象徴である「高炉」の廃止をあっという間に次々と決定し、長年供給先に握られていた価格主導権を、値上げに踏み切ることで取り戻し、提供する製品の付加価値を高めることに成功した。その傍ら海外事業を拡大すべく矢継ぎ早の巨額投資に打って出た。10万人以上の従業員を抱える大きさこそ変わらないが、その重厚長大な企業体質の足取りは明らかに軽くスピイーディーになった。
極め付きが、直近大きくニュースとなっている2023年12月に日本製鉄が決断した米大手USスチールの買収だ。その額、なんと2兆円。日本製鉄がこれほどまでの巨費を投じて米国に根を下ろそうとするなど、多くの人々は考えもしなかった。日本製鉄のここ数年の変貌ぶりを振り返れば、この野心的な挑戦すら必然のように見えてくる。「前例なんて気にするな。道理に合うことを信じてやり抜け」ジリ貧の日本製鉄を変えたのはかつて社内では異端とみられていた人物(橋本社長)だった。だがそのやり方は決して奇をてらったものではない。やらなければいけないことを、どれだけ早く大胆に進められるか…。リーダーとして自ら範を示し、社員たちを叱咤激励した、鈍重だった巨像が、世界で勝つために軽やかに走り出したのだ。
橋本氏は、日本製鉄にとって「異質」の存在である。合意形成を重んじ、慣例を大事にする社風にあって橋本氏は組織の空気を意に介さず、日本製鉄が今やらなければならないことを最短距離で実行してきた。しがらみに縛られがちな大企業のトップでありながら、ここまで振り切った行動ができる人はなかなかいないだろう。そしてこの異質さこそが企業経営の「王道」なのではないだろうか。「改革」を叫ぶ経営者は多いが、一体どれほどの覚悟を持って会社を変えようとしただろうか?橋本氏はリーダーとして本質的な課題をあぶり出し、リスクを取って改革を有言実行し続けた。それが日本製鉄という巨漢を変えた。橋本氏の姿は日本の企業トップに覚醒を促しているように見える。「日本製鉄の転生(上阪欣史著・日経PB社)」 このようなかつての大企業・日本製鉄の躍進は、今後の日本の経済の見通しの明るさを強調するものであると考えるが、あらためて我がサントリーのここ直近の30年の歩みを振り返ってみると、この日本製鉄と似たような内容に映っていると感じているのは私だけではないと思っています。ちょうど30年前の1994年(平成6年)を思い起こせば、この時代はウイスキーの長期低落傾向に歯止めがかからず、その需要は毎年2割程度ずつ減り、経営の屋台骨だった洋酒事業に赤ランプが点り始めていました。起死回生を狙って次から次へと新商品を導入し、新たな飲み方訴求で積極的なマーケティングを展開したにもかかわらず、なかなか需要は回復せず、全社の売上・利益も低迷する一方だった。まさにウイスキー苦難の時代と言えます。
このようなかつての大企業・日本製鉄の躍進は、今後の日本の経済の見通しの明るさを強調するものであると考えるが、あらためて我がサントリーのここ直近の30年の歩みを振り返ってみると、この日本製鉄と似たような内容に映っていると感じているのは私だけではないと思っています。ちょうど30年前の1994年(平成6年)を思い起こせば、この時代はウイスキーの長期低落傾向に歯止めがかからず、その需要は毎年2割程度ずつ減り、経営の屋台骨だった洋酒事業に赤ランプが点り始めていました。起死回生を狙って次から次へと新商品を導入し、新たな飲み方訴求で積極的なマーケティングを展開したにもかかわらず、なかなか需要は回復せず、全社の売上・利益も低迷する一方だった。まさにウイスキー苦難の時代と言えます。
一方では、1964年に進出したビール事業は40年以上もの間、赤字を出し続け、経営の大きな足かせになっていて、それまではウイスキー事業で得た利益によってビール事業の赤字を補填し続けてきたのですが、このウイスキーの衰退によって、全社的な経営が立ち行かなくなってきたのがまさにこの頃でした。このままでは会社の存続が危ぶまれると社内に危機感が走っていたのを鮮明に記憶しています。「この時がサントリー最大の危機であった」とのちのちサントリーの佐治信忠会長は語っています。
そのような苦境の状態を脱するきっかけとなったのが飲料事業でした。一時は経営難に陥っていた飲料事業だったが、時期を同じくした1992年、缶コーヒー「BOSS」の大ヒットを皮切りに、「サントリー天然水」とともに2本柱で飲料事業の柱が確立し、飲料事業が独立した収益の柱として急成長したことで、ウイスキー事業の目減り分をうまくカバーする結果になりました。そして2004年に発売されたサントリー緑茶「伊右衛門」が大きく市場を拡大し、サントリーの飲料事業は盤石な基礎を築くこととなります。この状況は、まさに「渡りに船」といえるでしょう。その後、飲料事業は海外展開をめざしてアジアやヨーロッパの飲料会社を次々と買収しながら急成長し、2014年、飲料事業単体の会社として「サントリー食品インターナショナル」が東京証券取引所市場第一部に株式上場をを果たすことになります。 一方、赤字続きだったビール事業の30年を振り返ってみると、ちょうど30年前の1994年、発泡酒の先駆けである「ホップス<生>」が発売されました。バブル経済の後、低価格輸入ビールが登場する中、美味しくて、かつ価格面でも喜ばれる商品の開発が具体化したのです。安価でうまい発泡酒市場を形成する起点となりました。しかしビール全体の事業としては採算に乗るにはまだまだ力不足でしたが、その10年後の2004年、現在のサントリーのビール事業の中核ブランドである「ザ・プレミアムモルツ」が生まれました。「本場ヨーロッパで認められる世界最高峰、最高級のピルスナービールを造る」という思いを込めたその品質はモンドセレクション、ビール部門最高金賞を3年連続で受賞するという快挙を成し遂げました。そしてその3年後発売された発泡酒・「サントリー金」麦がヒットし、ロングセラーヒットとなり消費者に大きく支持されたことで、ビール事業の収益も大幅に改善されることに至ったのです。
一方、赤字続きだったビール事業の30年を振り返ってみると、ちょうど30年前の1994年、発泡酒の先駆けである「ホップス<生>」が発売されました。バブル経済の後、低価格輸入ビールが登場する中、美味しくて、かつ価格面でも喜ばれる商品の開発が具体化したのです。安価でうまい発泡酒市場を形成する起点となりました。しかしビール全体の事業としては採算に乗るにはまだまだ力不足でしたが、その10年後の2004年、現在のサントリーのビール事業の中核ブランドである「ザ・プレミアムモルツ」が生まれました。「本場ヨーロッパで認められる世界最高峰、最高級のピルスナービールを造る」という思いを込めたその品質はモンドセレクション、ビール部門最高金賞を3年連続で受賞するという快挙を成し遂げました。そしてその3年後発売された発泡酒・「サントリー金」麦がヒットし、ロングセラーヒットとなり消費者に大きく支持されたことで、ビール事業の収益も大幅に改善されることに至ったのです。
赤字続きでお荷物だったビール事業の収益改善の兆候が見え始めた中で、こんどは2010年前後からウイスキーが「角ハイボール」によって再び消費者に支持され復活し、ふただひウイスキープームが到来しました。そしてそれは日本の高級ウイスキー(響・山崎・白州など)が世界に大きく評価され大きく伸長するという流れになります。そしてさらにその数年後の2014年、勝負の時がやってくる。サントリーホールディングスは米の大手蒸留酒会社であるビーム社を約160憶ドル(1兆6,500億円)で買収し、蒸留酒市場で世界3位の座を手に入れる。社運をかけた大勝負は10年経った今、同社の持続的成長の基盤となっている。
このようにサントリーの30年を振り返ってみると「日本の失われた30年」とはうって変わって「苦しい中でも挑戦し成長し続けた30年」だったように思えてきます。実際の売上高をこの30年間で比較してみると2004年の全社の売上高が約7,300億円だったのに対して、昨年度2023年度のグループ売上高が3兆3,000億円と約4.5倍になっていることからも、その成長ぶりがはっきりと伺えます。日本の大手企業が混迷を極める中、このような飛躍的成長を成し得たのはどうしてなのか…? 以下に、この期間に会社と共に汗を流してきた私の所見を述べさせてもらいたいと思います。 前述したように環境変化の激しい時代には、企業が長年培ってきた強みを発揮できるビジネスモデルはそう長くは続きません。そのビジネスモデルを守ろうとすればするほど、経営者は短期的な視点に捕われ、中長期的な発想や観点を見失いがちになる。しかし時代が変わろうとも企業として大事に受け継いでいかなければならない理念や価値観までも変えてしまうことは、その会社の存在意義を棄損してしまうことにもなりかねません。それは私が30代だった頃、何度も「不易流行」という言葉を耳にしていたことを思い起こさせます。当時の社長であった佐治敬三氏は「不易流行研究所」という部署をつくったほど、この言葉を何度もよく口にしていて、その主義主張は、「経営とは不易流行の本質を知ることにある」ということを常に語っていました。
前述したように環境変化の激しい時代には、企業が長年培ってきた強みを発揮できるビジネスモデルはそう長くは続きません。そのビジネスモデルを守ろうとすればするほど、経営者は短期的な視点に捕われ、中長期的な発想や観点を見失いがちになる。しかし時代が変わろうとも企業として大事に受け継いでいかなければならない理念や価値観までも変えてしまうことは、その会社の存在意義を棄損してしまうことにもなりかねません。それは私が30代だった頃、何度も「不易流行」という言葉を耳にしていたことを思い起こさせます。当時の社長であった佐治敬三氏は「不易流行研究所」という部署をつくったほど、この言葉を何度もよく口にしていて、その主義主張は、「経営とは不易流行の本質を知ることにある」ということを常に語っていました。
不易流行とは、「変わることのないものと、変化し続けるもの」。これを企業の経営としての言葉に置き換えると、経営理念などの企業の本質的な考え方をブラさずに、時代の変化に応じて新しい事業分野や手法などを取り入れていくこ
これをサントリーの経営にあてはめると、「不易」=変えないものは「現状に甘んずることなくリスクを恐れず挑戦すること(やってみなはれ)」で、「流行」=変えるものは、時代の流れに合わせて扱う商品・サービスやそれを提供する市場や顧客ということになります。日本で初めてウイスキー事業への挑戦し、遅れて参入し、苦戦を強いられたビール事業、再興させた飲料事業のグローバル展開、思い切った海外大型企業の買収等、厳しい環境の中にあってもサントリーは常にあきらめず、へこたれず、しつこく数多くの分野で現状に満足することなく挑戦を続けてきたのです。 かつての日本の旧来型企業の代表格であった日本製鉄が見事に復活できたのも、従来からの強みであった製鉄という主力事業の品質を高めていくという理念をブラざずに、従来の商慣行や旧来型のビジネスモデルの改革を敢行した経営者の存在があったからだと考えています。日本経済の復活の「鍵」は、日本を代表する企業が、まさにに日本が過去から培ってきた日本的経営の理念を大切にしながら、どんどん新たなビジネスモデルの創出に向けて持てる経営資源に積極的に投資し、新たなチャレンジをし続けることにあると考えています。そうすることで日本の中に、また新たな成長企業が生まれる素地を作ることにもつながります。
かつての日本の旧来型企業の代表格であった日本製鉄が見事に復活できたのも、従来からの強みであった製鉄という主力事業の品質を高めていくという理念をブラざずに、従来の商慣行や旧来型のビジネスモデルの改革を敢行した経営者の存在があったからだと考えています。日本経済の復活の「鍵」は、日本を代表する企業が、まさにに日本が過去から培ってきた日本的経営の理念を大切にしながら、どんどん新たなビジネスモデルの創出に向けて持てる経営資源に積極的に投資し、新たなチャレンジをし続けることにあると考えています。そうすることで日本の中に、また新たな成長企業が生まれる素地を作ることにもつながります。
詰まるところ今後の日本企業の発展に必要なのは大企業であれ、中小企業であれ「経営のトップの覚悟」に尽きるのではないかと考えています。単に短期的な売上や利益を負うのではなく、広い視野に立って社会への貢献につながる大きな夢を描き、その夢に向かってリスクを恐れず挑戦し続ける姿勢を社内外に示し、それを何度も何度もしつこく言い続けることで従業員が一丸となってその夢を追い続けるようになる、そんなタフな会社が今後の日本を大きく引っ張っていのまではないかと考えています。
「『理念が大事だ』というのは口で言うことはできても、体現することは難しい。短期利益とコンフリクトを起こしたときに、本当に理念を守り切れるか。そこまで理念というものの力を信じることができるかどうかということが、企業のトップには問われている。人に何か伝えようと思ったら、一度では足りない。100回でも足りない。1,000回でも足りない。自分が心から信じることであれば、何度でも言い続ける気持ちがないと大きな組織を導くことはできない。一万回でもダメなら、10万回かもしれない。同じ言葉を飽きずに言い続けるのが経営者の役割です」と、私が最も敬愛するサントリーの佐治信忠会長は語っています。
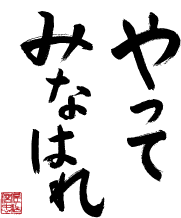


コメント
COMMENT